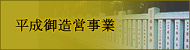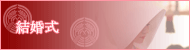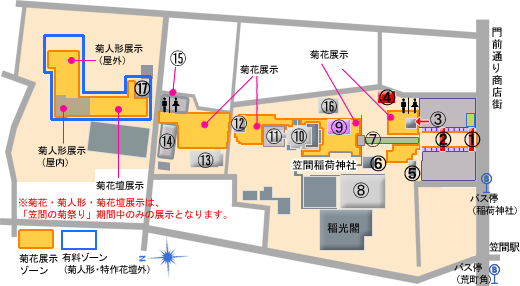 |
||||
 一の鳥居 一の鳥居 |
 車祓所 車祓所 |
 御本殿 御本殿 |
 聖徳殿 聖徳殿 |
 二の鳥居 二の鳥居 |
 楼門 楼門 |
 末社 末社 |
 瑞鳳閣 瑞鳳閣 |
 手水舎 手水舎 |
 社務所 社務所 |
 嘉辰殿 嘉辰殿 |
|
 東門 東門 |
 藤棚 藤棚 |
 美術館 美術館 |
|
 絵馬殿 絵馬殿 |
 拝殿 拝殿 |
 休憩所 休憩所 |
|
鳥居は神社を表示し、また神社の神聖さを象徴する建造物ともいえます。 |
鳥居の起源については、天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋にお隠れになった際に、八百万の神々が鶏を鳴せましたが、このとき鶏が止まった木を鳥居の起源であるとする説や、外国からの渡来説などがあります。 |
|
参拝に先立ち、身を清める場所です。詳しくは「手水の作法」のページをご覧下さい。 |
文化13年に再建された入母屋造りの建物です。左右には奉納の毛綱があります。 |
|
明治32年、間口六間、奥行き三間、入母屋瓦葺で柱14本の吹き抜け造りです。 |
事故を起こすことなく過ごせるように、運転免許取得日や誕生日、車の購入日などを皆様の佳き日と定めて交通安全祈願を斎行しています。 |
|
「萬世泰平門」と言い、重層入母屋造で昭和36年に竣工の建物です。扁額は当時の神宮祭主、北白川房子様の御染筆によるものです。 |
境内の2株の藤樹は樹齢400年に及ぶもので、昭和42年に県の天然記念物に指定されており、内1本の八重藤は花が葡萄の実のように集合して咲く珍しい種類です。 |
|
昭和35年10月の竣工で、神社建築の美と現代建築の粋を集めた豪壮かつ華麗な建物です。 |
江戸時代末期、当時の名匠たちの手により施されました。昭和63年、国の重要文化財に指定されています。 |
|
稲荷大神様に由縁のある神様が祀られています。(詳しくはこちらをご覧下さい。) |
奈良の正倉院を模した建物で、昭和56年に開館されました。中世六古窯の古陶器を常設展示しています。 |
|
聖徳太子がお祀りされています。笠間施工組合(大工職)が中心に太子講が組織されています。 |
大正天皇御即位記念(大正6年)に建てられました。 |